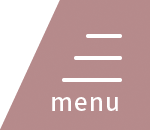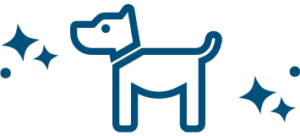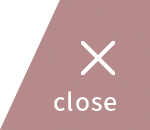もくじ
1. ごあいさつ
3.最後に
ごあいさつ
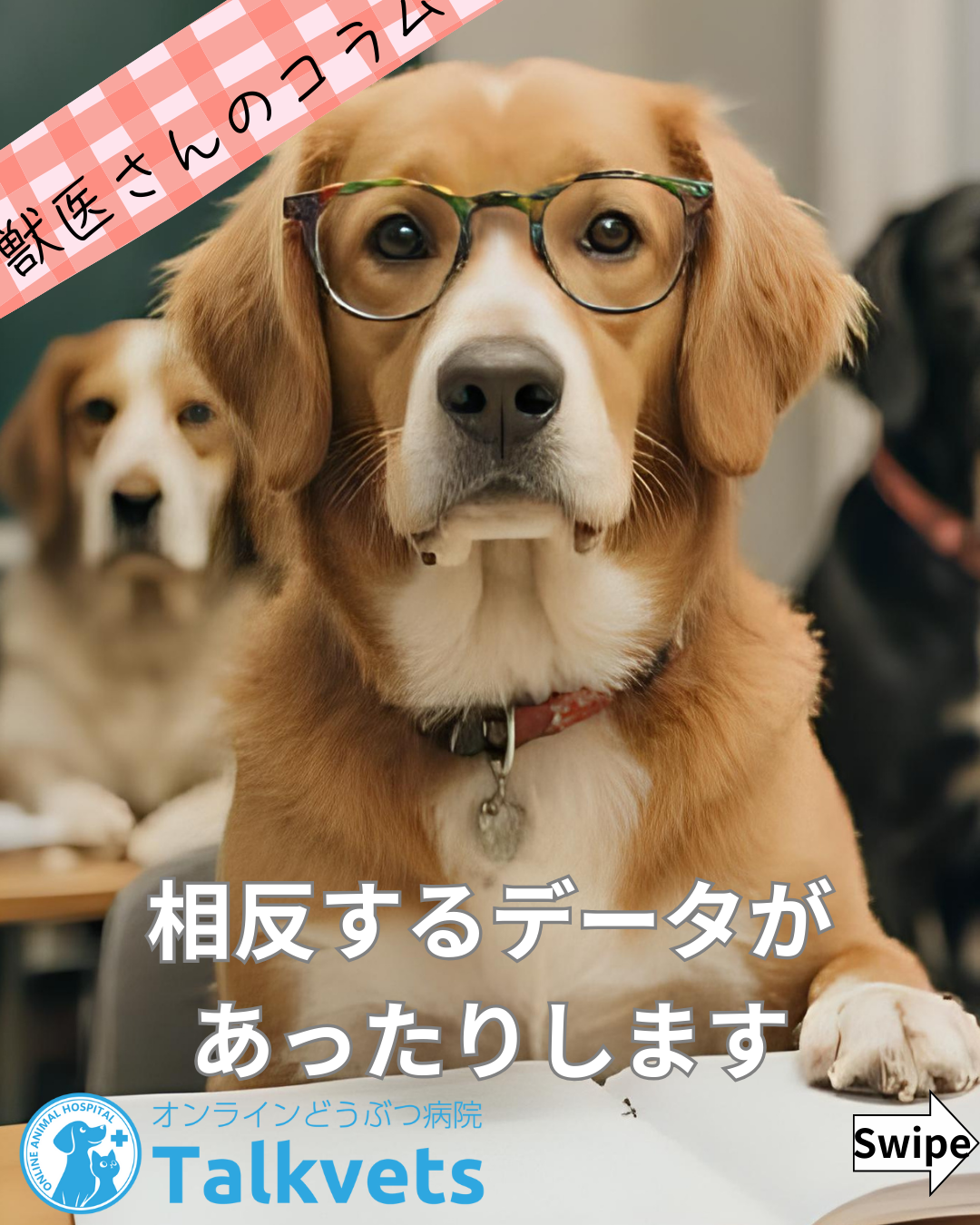
こんにちは。
オンラインどうぶつ病院Talkvets獣医師の前田です。
少し間があいてしまいましたが、本日は動物さんも関節はお大事に!の番外編として関節サプリの話をしたいと思います。
この関節サプリに関しては色々と難しい側面もあるのでそういった話もしていきたいと思います。
獣医さんが解説する関節サプリの実際 part.1

サプリメントの有効性の解釈は難しい
皆さんはどういう基準でサプリメントを選んでいるでしょうか?
よく知らない成分より、やっぱり聞いたことのある成分が入っていると良さそうな気がするのではないかと思いますがどうでしょうか?
関節サプリメントは特にその傾向がとても強い分野で、TVの影響なのかグルコサミンとコンドロイチンが圧倒的な知名度を誇っています。
そして、厄介なのがサプリメントのCMにはどれくらいの有効性があったというようなことも書いてあるので、知名度+有効性の証拠が揃うと効きそうと思ってしまうということです。
実際に、この2つの成分には有効性を示すデータがあります。
ただ、あまりかわらなかったというデータもあるのです。
何かの効果を証明するとき、基本的にはその結果には再現性があるはずで、同じような研究をすると同じような結果が出るはずです。
ではなぜ、相反する結果があるかというと、
一つは、その研究のスポンサーをしているのが開発会社であるということです。
自社で研究をせず、大学などに依頼している場合があり、
委託されている場合、研究費を出すスポンサーに対して忖度という名のバイアスがかかっている場合があります。
データを改竄しているというわけではなく、有効であるという結果がでやすく研究を設計していたり、解釈している場合があるということです。
2つ目は、研究の設計にも関わってくるのですが、
動物の症状の改善に対する評価をするときに、
・飼い主さんや獣医師の主観的な判断によるスコアだけを評価基準としている
主観的なスコア化ももちろん大切なのですが、研究としての信頼性を求めるには客観的なデータが必要になってきます。
最近では、ground force plate(床反力計)などの床を踏むときの力の違いを記録し、改善の有無を客観的に評価するという方法も取られています。
・ランダム化していない
年齢や性別や体重などの個々の条件を見ずにランダムに投与群と非投与群に振り分けて偏りがないようということがされていない。
・二重盲検試験をしていない
評価する側も何を投与しているのかがわからない状態、つまり同じ形状のものを投与しているが、評価しようとしている成分が入っている子と入っていない子がいて、それを飼い主さんも獣医師も知らない状態で評価してもらうことで偏りをなくすよな工夫がされていない。
などなど研究の仕方で信頼度がかわってくるということがあります。
パッと見は同じような研究でも、こういった研究設計の仕方次第で、良い結果が出ていてもあまり信頼できないということが起こりえるのが難しいところです。
実際、獣医さんでも広告だけをみて、そのデータが信頼できるものかを判断するのは難しいです。(元になっている論文を探して読まないとわかりません汗)
難しい業界ですよね…
国際的なガイドラインでの推奨について
結論からいうと、今現在、関節サプリとしてグルコサミンやコンドロイチンの推奨度は知名度ほど高くないと考えられています。(効果が全くないというわけではありませんので注意!)
じゃあ、どれがいいのか?という話なのですが、
一応の目安として、COAST Development Groupという欧米・アジア・豪州など複数国からの獣医師、整形外科専門医、リハビリ・理学療法の専門家、疼痛管理の専門家を集めた組織委員会が、2023年に国際合意治療ガイドライン(COAST 2023)を発表しているのでご紹介したいと思います。
そのガイドラインによれば、今のところ1番推奨度が高いのがオメガ3脂肪酸で、
炎症の軽減、疼痛スコアの改善に効果があり、食事に添加されている製品(関節用の療法食)があり続けやすいということも指摘されています。
ちなみに、栄養のガイドラインではEPA+DHAの合計量が1kgあたり50~220mg/日が効果的とされていますが、多くの研究では1kgあたり~100mg/日前後で有意な跛行改善効果や疼痛軽減効果が得られたと報告されています。
それに基づいて、ロイヤルカナン、ヒルズなどの関節療法食では1kgあたり100mg/日以上になるように設計されています。
最後に
またまた、サプリメントの話を書いているとどんどん長くなってしまったので、Part.2に続けようと思います。
ちなみに、COASTはわんちゃんでの話なのでご注意くださいね。
オメガ3脂肪酸以外に関節症に効果が期待できる成分の話を次回する予定です。
ねこちゃんはわんちゃんと違って研究が進んでいないところも多いのでどこかでそんな話も書きたいと思っています!
それでは、また次回のコラムでお会いしましょう!

執筆者
2010年 北里大学獣医学部卒業
大阪、東北の動物病院を経て、
2015年~2016年 北里大学附属小動物医療センター研修医
2016年~2024年 大阪市内の動物病院の開業業務にたずさわり、院長として勤務
2024年 オンラインどうぶつ病院Talkvets立ち上げ