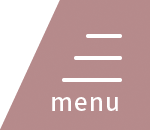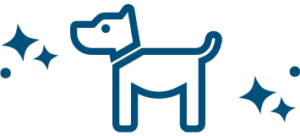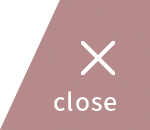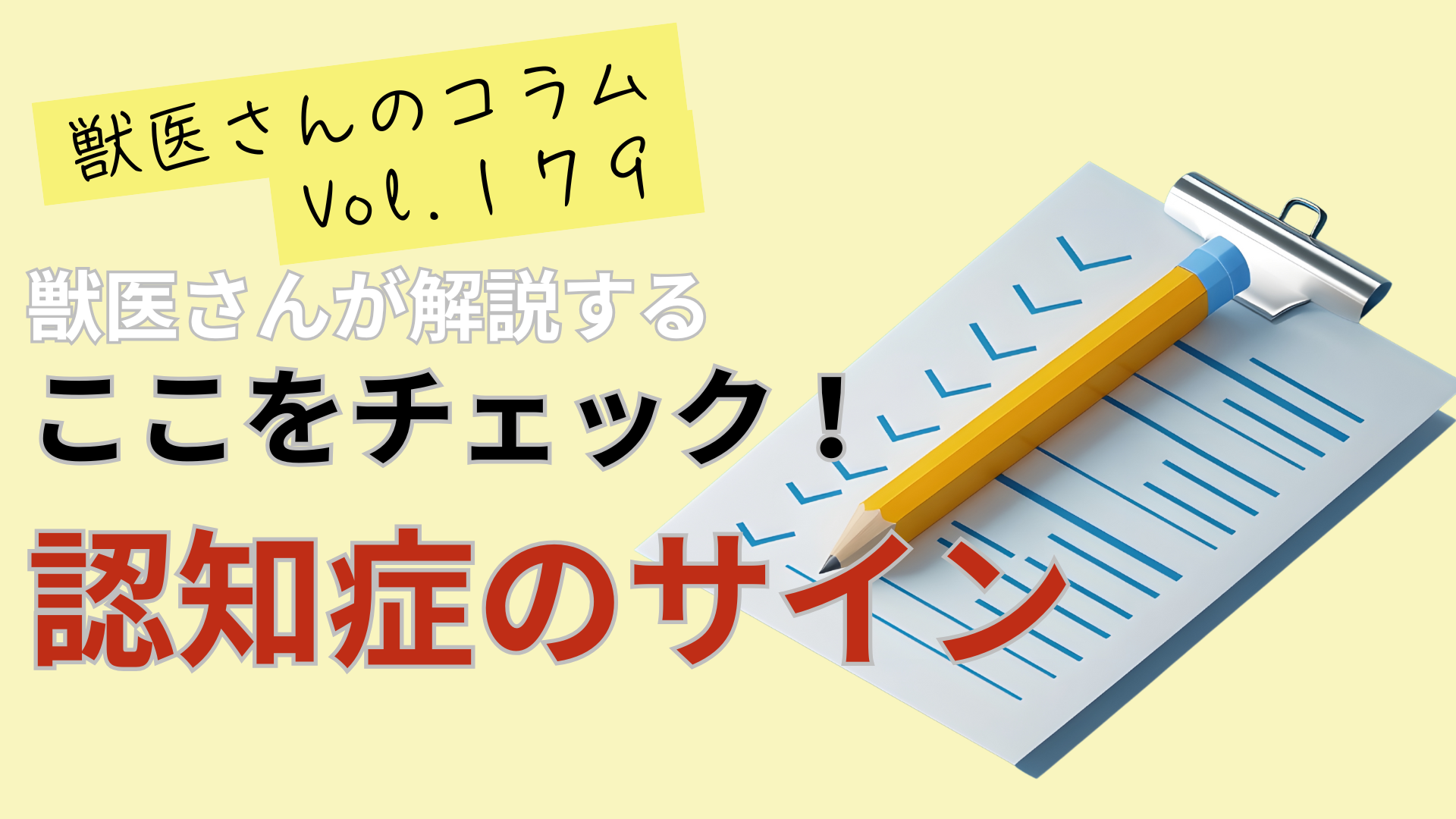
もくじ
1. ごあいさつ
3.最後に
ごあいさつ

こんにちは。
オンラインどうぶつ病院Talkvets獣医師の前田です。
今日は昨日に引き続き、認知症の話をしたいと思います。
今日のテーマは症状と獣医さん的な見極めポイントなどです。
昨日の話題でも触れた通り、高齢になってくると認知機能の低下が何かしら出てくる可能性があるので、シニアの子はぜひ認知機能のチェックをしてみてくださいね!
獣医さんが解説するここをチェック!認知症のサイン

認知症の症状って?
認知症自体はわんちゃんでもねこちゃんでも起こりますが、わんちゃんの典型的な認知症の症状はDISHAAという頭文字で6つに分類されて病院などの診断に使われています。
その6つの症状とは、
①D:見当識障害
場所・人・時間の感覚が混乱してしまい、例えば、家の中で迷ったり、壁を見つめたりといった行動がでてきます。
②I:交流の変化
飼い主さんや他の動物との関係変化し、飼い主さんに関心を示さなくなったり、逆に過度に甘えたり、吠えるようになったり攻撃的になったりと性格がかわったようになります。
③S:睡眠リズムの変化
これもよくある症状ですが、昼夜逆転・不眠・夜鳴きをするようになります。
④H:排泄の失敗
トイレの場所を忘れて、室内で失禁したり、トイレとは違う場所で排泄したりすることもでてきます。
⑤A:活動性の変化
運動量・興味の低下によって、遊ばなくなったり、散歩に行きたがらなくなったり、ぼんやりしたりといった様子が出てきます。
⑥A:不安な行動
不安な気持ちになったり、過敏に反応したりということも出てきます。
例えば、落ち着かずに歩き回ったり、過度に吠えてしまったり、分離不安のような症状が出ることもあります。
初期は、散歩中に方向を間違える、寝つきが悪くなるなどの軽度の混乱と夜の覚醒などから始まり、さらに進んで中期になると、名前を呼んでも反応しない、トイレ失敗、夜鳴きなど記憶障害や社会的な反応の低下が出てきます。
後期では、食事を忘れる、同じ場所をぐるぐる回る、反応が乏しくなり生活の介助が必要になってきます。
一方で、ねこちゃんの場合は、わんちゃんほど普及はしていないもののVICDという頭文字で4つの症状に分ける方法があります。
①V:発声の変化
高齢期のねこちゃんでよくある夜鳴き、要求鳴き、意味のない鳴き声も認知機能の低下の症状です。
ただし、甲状腺機能亢進症など他の病気でも起こりうる症状なので注意が必要です。
②I:交流の変化
飼い主さんや他の動物との関係変化はわんちゃんと同様に起こってきます。
甘えなくなったり、飼い主さんへの反応が変わってくることや逆に昔より甘えるようになったという場合もあります。
③C:睡眠リズムの変化
これもわんちゃんと同様ですが、ねこちゃんは寝ている時間の長い動物なので、少しわかりにくい場合もありますが、よく夜中に鳴くようになって症状がわかることが多いです。
④D:見当識障害
わんちゃんでも出てきましたが、空間の把握ができなくなったり、時間がわからなくなったりという症状はねこちゃんでも起こります。
ここをチェック!
次に、獣医さん的な認知障害を疑うポイントがあるのでそれもちょっとお伝えしたいなと思います。
わんちゃんやねこちゃんを診察していると、緊張していたり、怖がっていたりといつもと違う反応をするのですが、特に問題ない子たちは必ず目に表情があります。
でも、少し認知障害を疑う子たちは、わんちゃんもねこちゃんも共通して目の表情がなくなってくるというか、少し虚な目をしてきます。
ぜひ、目に注目してみてみてください。
後ずさりできるかもポイントの一つかもしれません。
若い子だと、特に問題なく後ずさりできるのですが、認知障害が出てくると後ろに下がることができなくなってきます。
よく、狭いところに入って出れなくなるというのもこのせいです。
なかなか、テストするのが難しい項目ですが狭いところ注目してみてみてください。
あとは、大好きなおやつやおもちゃに対する反応や、名前を呼んだ時の反応、アイコンタクトが取れるかどうかといったこともお聞きして判断材料にしています。
最後に
お年をとってくると、多かれ少なかれ認知障害というのは出てくると思いますが、注目してほしいポイントはどれくらいの速度で進行していくかというところです。
あれ?っと思ったらぜひこの症状の分類を使って、症状が増えていかないか、悪化していかないかをチェックしてもらうといいと思います。
また、余力があれば、明日は予防や治療の話を書く予定なので、日常に取り入れてもらえたらと思っています。
それでは、また次回のコラムでお会いしましょう!

執筆者
2010年 北里大学獣医学部卒業
大阪、東北の動物病院を経て、
2015年~2016年 北里大学附属小動物医療センター研修医
2016年~2024年 大阪市内の動物病院の開業業務にたずさわり、院長として勤務
2024年 オンラインどうぶつ病院Talkvets立ち上げ