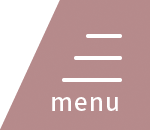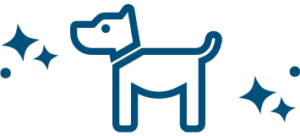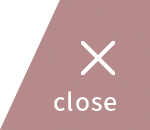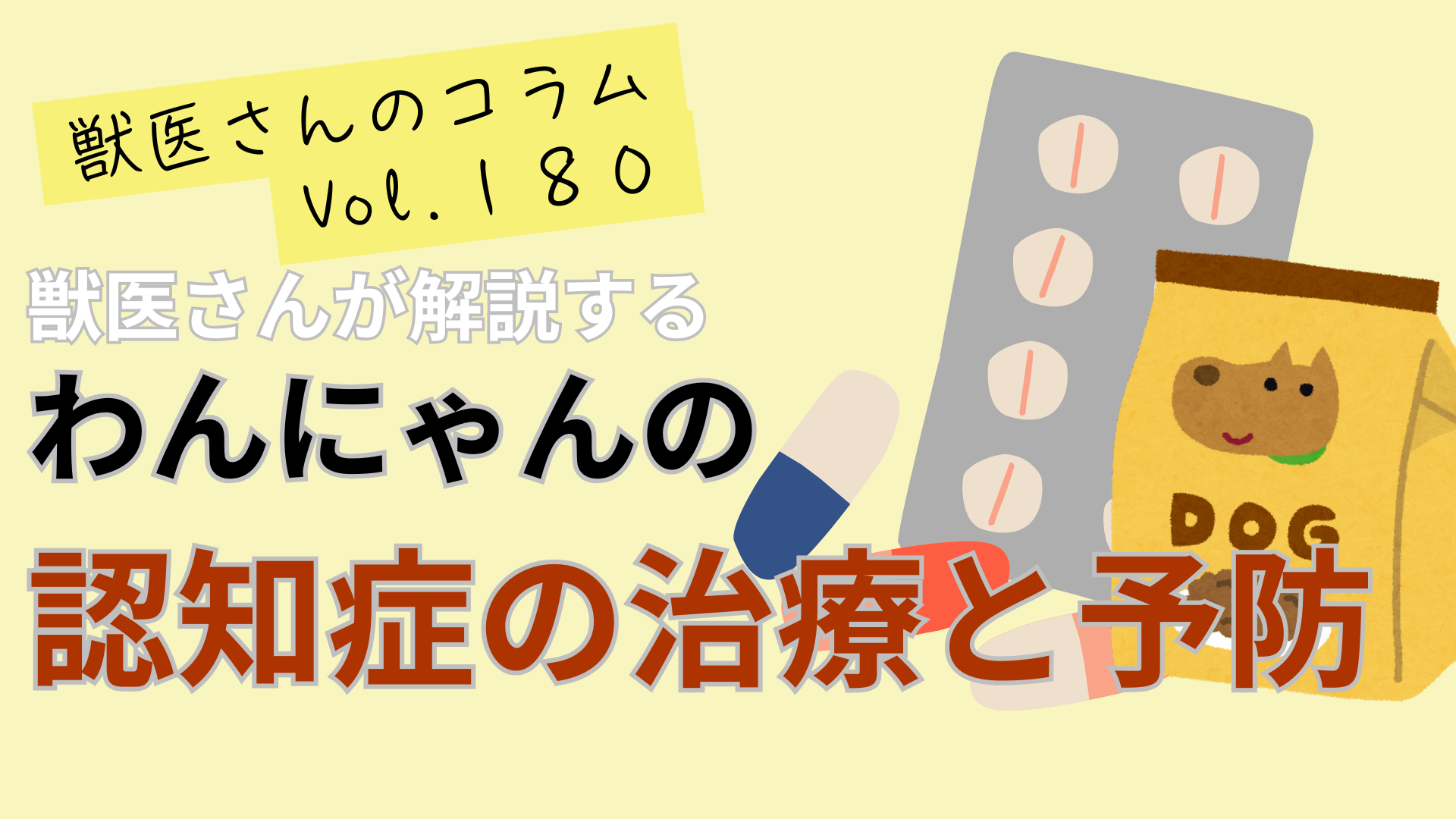
もくじ
1. ごあいさつ
3.最後に
ごあいさつ

こんにちは。
オンラインどうぶつ病院Talkvets獣医師の前田です。
今日は、認知症シリーズ第3回として治療や予防の話をしていきたいと思います。
まだ本格的に治療している人は少ないかもしれませんが、今から発展していく可能性のある分野だと思います。
獣医さんが解説するわんにゃんの認知症の治療と予防

今までの治療
認知症という症状自体は昔からあるものでした。
ただ、なかなか治療となると難しい面が多かったと思います。
それには色々と理由があるのですが、獣医さん側も何かしらのデータがあるもので紹介できるものが少なかったというのも一つですし、加齢のせいだからということで治療を考える機会が少なかったというのもあるかもしれません。
従来の治療は、主に環境の整備のアドバイスと夜泣きに対する睡眠薬の処方がメインだったと思います。
ただ、最近は時代もすすんできて紹介できそうなものが増えてきたことや、人の世界でも認知症の治療という気運も高まってきたこともあり、少しずつではありますが、治療を積極的に考えられるところにきているのかなと思います。
最近の知見
まず、認知症の治療の柱は3つあります。
一つ目は、環境の整備や刺激です。
これは、予防という面でも使えると思います。
①同じ生活リズムにする
認知機能が衰えると、時間の感覚が狂いやすくなります。
そこで、散歩に行く時間やごはんの時間、夜暗くする時間など決まったルーティーンを整えることが一つ重要です。
②脳を刺激することも重要
ルーティーンを整えるとともに、刺激があることも重要なことです。
わんちゃんだと、ノーズワークやおすわりや待てなどのコマンドの練習なども取り入れやすいかもしれません。
③安全な動線の確保
滑らない床やスロープなど転倒しないように環境を整えていきましょう。
④スキンシップ
飼い主さんとの関係性もすごく大切です。
スキンシップする時間を意識的につくっていきましょう。
⑤感覚刺激の調整
認知機能が低下していくと、感覚が鈍くなる場合もありますし、感覚過敏になる場合もあります。
不安が強くならないように、音や光などの調整をしてあげてください。
これは一例ですが、昨日書いたように認知症の症状はある程度分類されています。
その子の症状にあわせた環境の整備と、予防もかねて刺激やスキンシップを考えていってもらえると良いと思います。
この環境や刺激などに関しては、ねこちゃんも同様に考えてもらって大丈夫です。
2つ目は、栄養介入です。
これは主にわんちゃんの話になってしまいますが、実はわんちゃんの認知症には効果が認められている成分が何個かあります。
①MCTオイル
認知症の脳では、脳でのグルコースの利用量が減ると言われており、その代替としてMCT(中鎖脂肪酸)が注目されています。
中鎖脂肪酸は肝臓で速やかにケトン体に変換され脳の代替エネルギーとして使われることがわかっています。
実際に、5.5%のMCTオイルを配合した食事で昼夜リズム・反応性・探索行動・学習記憶スコアの上昇が示されています。
②抗酸化成分のカクテル
複数の抗酸化作用のある成分をブレンドしたものが研究では使われています。
配合は様々なのですが、一例として、
抗酸化物質(ビタミン E、ビタミン C、α-リポ酸、セレンetc)
活性酸素や酸化ストレスを軽減し、神経細胞の損傷を防ぐ作用
オメガ3脂肪酸(DHA/EPA)
神経膜の流動性維持・抗炎症作用・シナプス機能維持
アルギニン
血管拡張・血流改善・一酸化窒素(NO)生成促進。脳の循環改善
ビタミンB群
高ホモシステイン血症や記憶・認知機能低下との関連から、脳代謝維持
などが使われています。
6.5%のMCTオイルを複数の抗酸化成分を併用することでも認知症状の改善が認められたというデータも出ています。
最後は、薬です。
現在、唯一の承認薬としてデータがあるのがセレギリンという薬です。(米国FDAで商品名 Anipryl®で正式承認されていますが、日本では未承認)
この薬は、脳内でドーパミンやノルアドレナリンなどの神経伝達物質の分解を抑え、神経伝達を活性化・酸化ストレスを軽減 する作用があり、単独使用で約75%の症状の改善効果があったと報告されています。
さらに、6.5%のMCTオイルと複数の抗酸化成分と組み合わせると約88%に反応があったというデータがあります。
お薬自体は、認知症シリーズの1回目に紹介したアミロイドβ(Aβ)に対するものではないので、今後アルツハイマー型認知症の薬などの動物医療での臨床応用の研究も進んでいくのではないかと期待しているところです。
知見を踏まえた治療と予防
さて、3本柱としてご紹介しましたが、実際にどういった戦略を立てられるかというところも少しお話したいと思います。
まず、予防レベルから始められるのは、環境整備や刺激のところだと思います。
わんちゃんの11〜12歳で約28%、15〜16歳で約68%が何らかの認知症症状が出るというデータや、ねこちゃんは11歳以上で約28%に軽度の認知機能低下、15歳以上では50%以上が何らかの認知行動変化がでるという話からすると10〜11歳を目安に予防を考えてみるというのがいいかもしれません。
次に、わんちゃんに関しては
認知機能の低下が出てきているのであれば、栄養介入を考えてもらっていいと思います。
正直な話、サプリメントとして抗酸化成分を配合したものは何個か出ているのですが、効果が出る配合かどうかはちょっと判断できないのがネックかなと思います。
もし、本格的に効果を出したいのであれば、医療用のドッグフードで、ピュリナプロのニューロケアは研究データに基づいた6.5%のMCTオイルや抗酸化成分を配合して作られています。
また、サニメドのニューロサポートも別の研究で使われていた配合量である5.5%MCTオイルと抗酸化物質が入っています。
どちらも、動物病院で購入しないといけませんが選択肢になるかもしれません。
さらに、薬の使用も考えられると思います。
薬に関しては国内承認がないので、動物病院で海外輸入薬として処方してもらう形であれば入手可能だと思います。
ただし、保険が効かないことが多いので、保険の内容などのチェックするとともに、現状では置いている病院を探すか、かかりつけの先生としっかり話をして輸入してもらう可能性を探っていく形になると思います。
最後に
わんちゃんやねこちゃんで認知症をどこまで病気ととらえて治療を提案していくかというのは獣医さんとしても今後の課題になってくると思います。
今日まとめた内容は段々かわっていくかもしれませんが、2025年版として一つの参考になれば幸いです!
それでは、また次回のコラムでお会いしましょう!

執筆者
2010年 北里大学獣医学部卒業
大阪、東北の動物病院を経て、
2015年~2016年 北里大学附属小動物医療センター研修医
2016年~2024年 大阪市内の動物病院の開業業務にたずさわり、院長として勤務
2024年 オンラインどうぶつ病院Talkvets立ち上げ