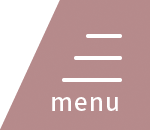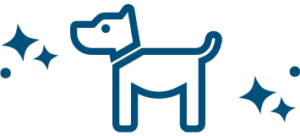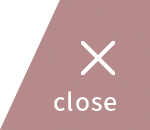もくじ
1. ごあいさつ
3.最後に
ごあいさつ

こんにちは。
オンラインどうぶつ病院Talkvets獣医師の前田です。
サプリメントの話を2日にわたって書かせていただきましたが、その中で少し触れた東洋医学についても書いてみたくなったので、本日は東洋医学についてお話ししてみたいと思います。
とはいっても、私は中獣医師(東洋医学を扱う獣医師)ではないので、東洋医学なども取り入れていらっしゃる患者さんたちを一緒に診させていただいた経験を元にして、どう考えるかというところにスポットを当てています。
獣医さんから見て東洋医学ってどう思う?

西洋医学と東洋医学
皆さん、病院に行ってツムラの漢方などを処方された経験がありませんか?
昔は、漢方といえばちょっと中華風の漢方薬局に相談するようなイメージでしたが、どんどんかわってきているなと思います。
実は、人医療でいうと、2002年から医学部で漢方教育が必須になり、病院での漢方の取扱も7割を超えているそうです。
つまり、今のお医者さんは西洋医学だけではなく中獣医学の一部も学ぶのがスタンダードになっているのです。
一方で、獣医療はというと、残念ながら教育課程で中獣医学を学ぶ機会はなく、卒後に自主的に勉強していく形になります。
つまり、今のところ動物病院は西洋医学のみ行っているのがスタンダードです。
獣医さんから見て東洋医学ってどう思う?
動物病院が、西洋医学メインで治療を行っていることは、決して悪いことではないと思います。
私も西洋医学獣医師なので、病気を診断して治すのには西洋医学が1番強いと思っています。
ただし、実際に治療にあたっている中で弱いなと感じている分野があることも事実です。
それは、体質による病気の発症を予防するという分野が弱いことと、慢性疾患を維持していく時に使える選択肢が少ないということです。
西洋医学は、病名をもとにして手術をしたり、薬剤を使って治すのはとても得意なのですが、免疫が過剰になりやすい、皮膚が弱い、お腹が弱いという各自の持つウィークポイントを補うのにはあまり適していません。
また、慢性疾患で使える薬がある程度決まってしまっているので、その薬でもうまく維持ができない時に困ることもあります。
そういったときに、もう少し東洋医学を標準治療に組み入れられたら治療の幅が広がるのではないかと感じることは多いです。
おすすめの使い方は?
とはいえ、病名がつくような病気には西洋医学のアプローチが適切だと思います。
なので、どちらか一辺倒になるのではなく、それぞれの得意・不得意を理解していいとこ取りをしていくのがいいのではないかと思っています。
具体的には、症状が強いときは西洋医学で診断名をつけて、治療する。
維持期に入ったら、東洋医学も取り入れて減薬の可能性を探る。
また、体質的に色々な病気になる頻度が多い子は、症状を出している時は西洋医学を使い、病気にならないように体質改善に東洋医学を使うというアプローチが有効なのではと思っています。
最後に
実は私も、中獣医学をいずれ学んでみたいなと思っていたりします。
必要な時に外科処置をためらわずに判断でき、必要があれば東洋医学の良いところも取り入れられるとホームドクターとして理想に近づけれるのではないかと思っています。
ちなみに動物病院でも、昔と違って中獣医学のみを行っている動物病院もありますし、どちらも行っているという病院も増えてきているので病院選びの参考にしてみてくださいね。
それでは、また次回のコラムでお会いしましょう!

執筆者
2010年 北里大学獣医学部卒業
大阪、東北の動物病院を経て、
2015年~2016年 北里大学附属小動物医療センター研修医
2016年~2024年 大阪市内の動物病院の開業業務にたずさわり、院長として勤務
2024年 オンラインどうぶつ病院Talkvets立ち上げ